自分で辞められるなら退職代行なんて必要ありません。
でも無理そうなら、この記事がきっと助けになるはずです。
[say name=”悩む男性” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/kaisya_man_bad-1.jpg”]
退職代行って名前は聞いたことあるけど、良く分かんないからどんなもんか教えて欲しい。
色々と聞きたいことや不安もあるな〜[/say]
ご覧頂きありがとうございます。そんな悩みを解決します。
元人材業界で営業をしていた僕が、客観的かつシビアにお伝えします。
[memo title=”この記事を読むと分かること”]
- 退職代行の仕組みや概要
- 退職代行を使う人が抱える理由
- 退職代行のデメリット
- おすすめ業者3選
- Q&A
[/memo]
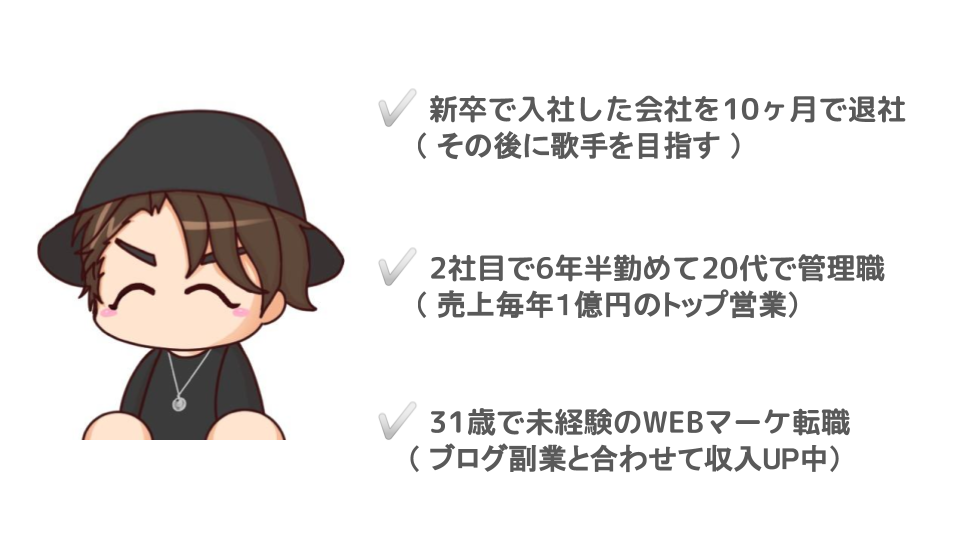
少し前から名前を聞くようになった『退職代行』ですが、実際どんなもんか知ってる人は多くないと思います。
今回は退職代行の仕組みや使うべき人、よくある質問への回答などを元人材業界の僕がお伝えします。
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]読み終わる頃には疑問が解消されて、自分は使うべきかどうか明確になってますよ。[/say]
仕事を辞める時に使える退職代行サービスとは?【仕組み】

少し前に登場して話題になった『退職代行サービス』ですが、内容をしっかり把握してない人も多いと思います。
なので、まずはざっくりとサービス内容についてお伝えします。
[list class=”li-check li-mainbdr main-c-before”]- サービスの概要
- 料金相場
- 使うときの流れ
退職代行とは最短即日で出社しなくてもよくなるサービス
退職代行とはあなたの代わりに会社に退職の意思を伝えるサービスです。
最短即日対応で、その日から出社しなくても良くなります。
サラリーマンが会社を辞める時は、本来2週間前に退職の意思を伝える必要があります。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
参照元:民法627条1項,Wiki
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]つまり即日で出社しないとなると、連絡をブッチしてバックレるしか方法はありません。[/say]
ただ、転職活動に支障が出たり、会社から訴えられたらと思うと不安ですよね?
そんな時、退職代行を使うと会社に連絡をしてくれるので、基本的にトラブルなく最短即日で出社しなくてもよくなります。
「それって違法じゃないの?」と思うかもですが、退職代行業者はあなたが辞めることを伝えるだけなので違法ではありません。
なぜなら、前述したように2週間前に伝えれば、いつでも辞められる権利を従業員は持っているからです。
ただし、業者が未払い賃金を請求したり、会社と交渉することは弁護士法の『非弁行為』に当たるので出来ません。
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]業界の注目度が増したことで、劣悪な業者が非弁行為に触れて問題になってるので注意が必要です。[/say]
退職代行の費用・料金相場はいくらくらい?
退職代行サービスは一般の業者で3〜5万、弁護士で5万以上が大体の相場です。
弁護士は少し高くなる分、サポート範囲が広がるので、不安を極限まで消したい人は検討の余地ありですね。
退職代行を使うときの流れ
退職代行の流れは大体一緒です。
- 申し込み
- ヒアリングシートの入力
- 料金の支払い
- サービス実行
- 退職に関する手続き
- (転職サポートを受ける)
ほとんどの業者は申し込みの前に『無料相談』を受けてるので、まずは問題なく辞められるのか確認してから依頼するといいですね。
退職後に転職活動をする人もいるので、転職サポートをしてる業者も多いです。
ただ、転職に関する記事を大量に書いてる僕からすると、退職後に転職活動をするのはおすすめしません。
なぜなら、リスクが大きいからです。
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]例えば、中々内定が決まらない時に、貯金が減っていくことで焦りを感じます。
その結果、本当はブラック企業なのに、内定が出たから入社してしまうなどが起こります。[/say]
理想は在職中に転職先を決めて、退職代行を使いスッパリ辞めることです。
もし、あなたの会社がブラック過ぎて、転職活動をする時間が全く取れない場合でない限りは。
なぜ退職代行を使う人がいるのか?【利用者が持つ理由】
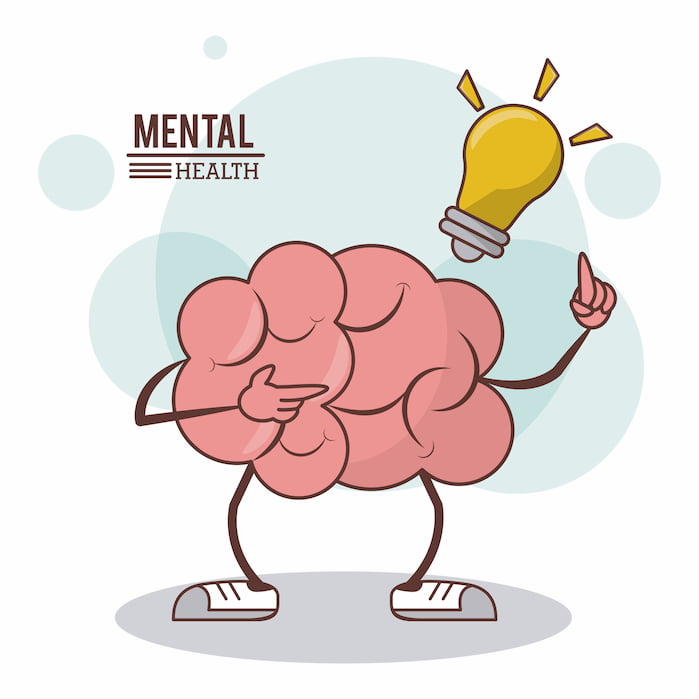
理由を細かく分けるといくつかありますが、大きくまとめると『自分で辞めると言えない』『辞めさせて貰えない』場合が多いです。
[alert title=”退職代行を使う人が抱える理由”]
- 上司が全然話を聞いてくれない
- ブラック企業で辞めると言ったら脅された
- 従業員が少なくて自分が辞めたら迷惑をかける罪悪感
[/alert]
繰り返しますが、従業員には辞める権利があるので、会社がそれを拒否することは出来ません。
しかし、いざ上記のような状況に直面すると「どうしたらいいの。。。」ってなるのも分かります。
決してその人が悪いわけじゃない。
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]そんなどうしようもない人の味方になるのが退職代行というわけですね。[/say]
退職代行のデメリット

退職代行サービスには最短即日で辞められるというメリットがある一方、デメリットも存在します。
- 退職は即日出来ないことが多い
- 訴訟を起こされた時に対処できない
- 未払い賃金の請求などの交渉は出来ない
退職代行業者はあくまで退職の意思を伝えるだけなので、トラブルが起こった時は対処できません。
また、サービス実行日から出社をしなくて良くても、前述した民法627条により、退社日がその日になることはほぼありません。
万が一のトラブルに備えるなら、後述する弁護士のサービスを使うのがベストです。
退職代行での失敗例やトラブル
この後で紹介する3社は失敗事例はないので成功率100%です。
しかし、下記の可能性はあるので頭に入れておきましょう。
- 会社から何度も連絡が来る
- 得意先から連絡が来る
本来、退職代行との間でやり取りは終わってるので、会社からの連絡に出る必要はありません。
しかし、書類や退職に関する手続きに何かしらの不備があると連絡が来る可能性があるので注意して下さい。
ちなみに引き継ぎをしてないため、得意先から連絡が来る可能性があるのは理解しておきましょう。
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]僕は退職代行を使ってはいませんが、何度も得意先から連絡がきましたw[/say]
おすすめ退職代行サービスまとめ【一般業者】

ここからは30社以上のサービスを見た僕が、ステマなしの本音100%で選んだ3社を紹介します。
金額や実績、サポート面などを総合的に見て判断しました。
[memo title=”おすすめ退職代行業者TOP3″]
- SARABA
- Jobs
- EXIT
[/memo]
詳しく知りたい人は退職代行のおすすめはココ!ランキングTOP3【大量の比較は不要】をご覧下さい。
各社の口コミも載せてるので参考になると思いますよ。
おすすめ退職代行サービスまとめ【弁護士】

すでにお伝えしたように、万が一のトラブルには退職代行業者では対処できません。
そこでおすすめが弁護士の退職代行サービスでして、下記が可能です。
[list class=”li-check li-mainbdr main-c-before”]- 未払い賃金などの交渉
- 労災の申請や慰謝料の請求
- 退職に伴う手続き(保険や年金など)の代行
正直言うと一般の退職代行業者を使っても99%はトラブルになりません。
ただ、「自分が残りの1%に入ったらどうしよう」と不安なのも当然だと思うので、気になる人は下記の記事をご覧下さい。
>> 関連記事:弁護士の退職代行はこんな人におすすめ【9割は不要】
弁護士・社労士・行政書士などの違いは?
色々な資格が出てきてワケわからなくなりますよね。
それぞれが出来ることを簡単にまとめたので参考にしてください。
| 資格名 | 交渉 | 裁判 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 可能 | 可能 |
| 特定司法書士 | 可能(140万円以下) | 可能(140万円以下) |
| 司法書士 | 不可 | 不可 |
| 特定社労士 | 可能 (相手が話し合いに合意した場合のみ) | 不可 |
| 社労士 | 不可 | 不可 |
| 行政書士 | 不可 | 不可 |
ただ、細かい違いを理解しても無意味なので、退職代行を選ぶ時は『全てが出来る弁護士』か『一般の業者』の2つだけ考えれば大丈夫です。
退職代行についてのよくある質問

最後によくある質問に答えていきます。
料金の支払い方法は?後払いは出来るの?
料金は銀行振込みやクレジットカードでの支払いをするケースが多いです。
基本的に先払いで入金が確認できてからサービス実行に移りますが、退職代行Jobsは翌月10日までの後払いにも対応しています。
>> 関連記事:退職代行Jobsの全て【アンチの僕が本音100%で語る】
有給の残りは消化出来る?
出来ます。
なぜなら、従業員が持っている有給の使用を会社が拒否する権利はないからです。
2週間以上の有給があれば、退職代行を使って明日から出勤しなくても有給消化日が退社日になるはずです。
有給なしの場合はどうなる?
入社したばかりなどで有給がない人は『欠勤扱い』になるので、欠勤分が月給から引かれることになります。
ただ辞めること自体はできるので問題ないですよ。
退職金はもらえる?
退職金は法律で決まってる訳ではないので、結論、会社の就業規則によります。
就業規則であなたが退職金をもらえる条件に該当していれば、基本的には問題なく貰えます。
規則を確認して、貰えそうなら退職代行から伝えてもらいましょう。
訴訟や損害賠償のリスクはないの?
完全にゼロとは言えませんが、基本的には考えにくいでしょう。
なぜなら、企業としては一個人に訴訟を起こすメリットがほぼないからです。コスパが悪すぎます。
ただ、劣悪な業者を利用して、非弁行為に触れた場合は訴えられる可能性もあるので、今回紹介したような信頼できる業者を選びましょう。
>> 関連記事:退職代行のおすすめはココ!ランキングTOP3【大量の比較は不要】
まとめ:退職代行を使う時は信頼できる業者を使おう
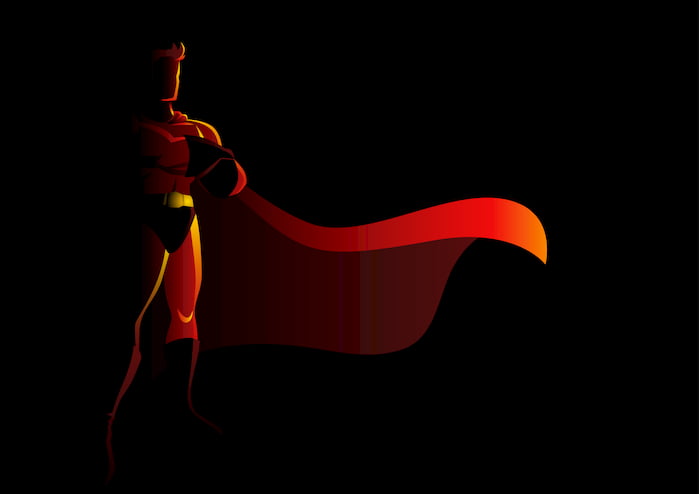
今回は『退職代行の全て』についてをお伝えしました。
[memo title=”今回のまとめ”]
- 退職代行とは最短即日で出社しなくても良くなるサービス
- 自分で辞めることが出来ない状況の人にはおすすめ
- 使う時は信頼できる業者を使ってトラブルを避けるべし
[/memo]
今回で退職代行について理解出来たと思います。
決して安くないので出来る限り使って欲しくないですが、あなたの助けになるのなら価値のあるサービスだとも思います。
もし使う決意をした人は下記の『おすすめ退職代行3社』を見て、ベストな業者を選んで下さい。応援してます!
[card id=”3483″]
[say name=”おけこ” img=”https://okekolog.com/wp-content/uploads/2020/01/httpf.hatena.ne_.jpfuku072520190625185020.jpg”]最後までご覧頂きありがとうございました!
この記事が良いと思ったらSNSでシェアして頂けると泣いて喜びますので良ければぜひ笑
>>感想をツイートして、おけこを泣かせる[/say]


コメント